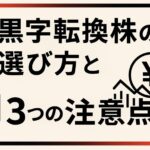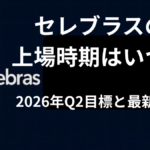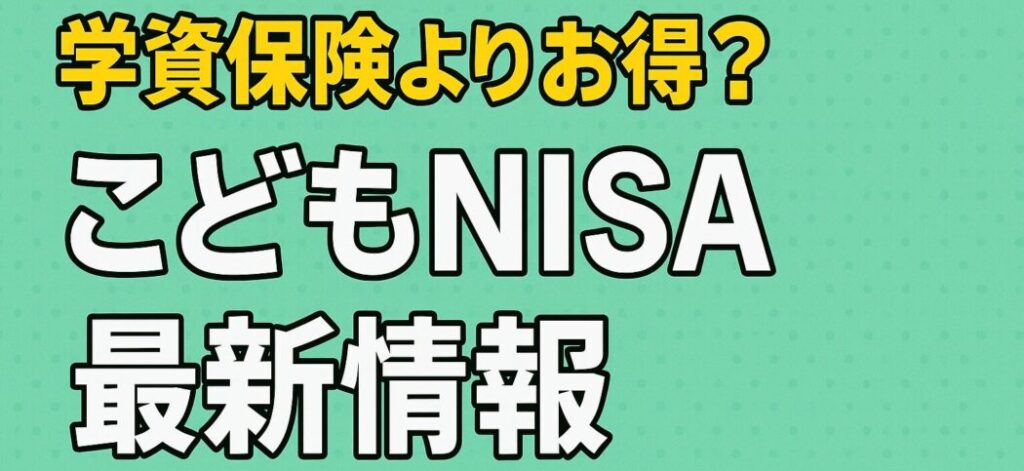
「学資保険とこどもNISA、どっちがいいの?」
――子どもの教育資金づくりに悩む方にとって、いま注目されているのが2026年にも導入が検討されている「こどもNISA」です。
従来のジュニアNISA終了後、どの制度を使えばよいのか分からないという声も多く聞かれます。
本記事では、こどもNISAと学資保険の違いをわかりやすく比較し、家庭に合った教育資金の準備方法を解説します。
制度の最新情報と、今できることを一緒に整理していきましょう。
こどもNISA(導入予定)とプラチナNISAの関係とは?
ジュニアNISAの終了と新たな制度検討
これまで未成年の資産形成には「ジュニアNISA」が活用されてきました。
しかし、18歳まで引き出しが制限されるなど使い勝手の悪さが指摘され、2023年末で新規受付は終了。
現在は未成年が利用できるNISA制度はありません。
こうした状況を受けて、政府は2026年度の税制改正を目標に、新たに「こども支援NISA(こどもNISA)」の導入を検討中です。
これは未成年にも一定の非課税投資枠を認め、教育資金づくりなどに活用できるようにする仕組みです。
プラチナNISAとは?実は高齢者向けの制度
一方で、同じタイミングで導入が検討されているのが「プラチナNISA」。
こちらは主に65歳以上の高齢者を対象とした制度で、分配型の投資信託などを新たに非課税対象とする案です。
混同されがちですが、こどもNISAとは対象年齢も制度内容もまったく異なります。
家族単位での非課税投資へ、制度の可能性が広がる
政府の方針では、こどもNISAとプラチナNISAは同時期に導入される見通し。
これにより、「家族全員でNISAを活用し、非課税で資産形成できる社会」を目指す動きが進んでいます。
特に子育て世代にとっては、教育資金づくりの選択肢が広がるのは大きなメリット。
こどもNISAはまだ構想段階ですが、今のうちから制度の概要を知っておくことで、先を見据えた準備が可能になります。
学資保険とこどもNISA(予定)を比較してみた

子どもの教育資金を準備する手段として、これまで主流だったのは「学資保険」。
しかし近年、資産運用の意識が高まり、投資による準備にも注目が集まっています。
ここでは、検討が進む「こども支援NISA(こどもNISA)」と学資保険を比較してみましょう。
運用の自由度と利回りの違い
| 項目 | 学資保険 | こどもNISA(予定制度) |
|---|---|---|
| 投資先 | 保険会社が運用 | 投資信託などを選んで自分で運用 |
| 利回り目安 | 年0.5〜1%程度 | 年3〜5%以上も可能(商品次第)だがマイナスも十分あり得る |
| 運用の自由度 | 契約時に固定 | 積立金額や商品を柔軟に変更可能 |
学資保険は安全性を重視した設計になっている反面、利回りは低め。
こどもNISAでは、投資信託などの金融商品を活用することでインフレに強い資産形成が可能になるかもしれません。
元本保証とリスクの違い
学資保険は原則として満期時に元本以上の返戻金が受け取れる設計になっています。
ただし途中解約すれば元本割れのリスクがあり、使い勝手は限定的です。
一方、こどもNISAは投資である以上元本割れのリスクがあります。
ただし、長期積立・分散投資を前提とする制度設計になるとみられ、時間を味方につければ安定した運用も期待できるというメリットもあります。
私の経験から、10年以上の長期積立であればマイナスになることはほぼありません。
資金の使い勝手と税制面の違い
| 項目 | 学資保険 | こどもNISA(予定制度) |
|---|---|---|
| 引き出しの自由度 | 満期まで原則制限あり | 目的問わず自由に引き出し可能 |
| 用途の制限 | 制限なし(教育用として設計) | 制限なし(使い方は自由) |
| 税制優遇 | 所得控除や控除枠あり | 運用益は非課税(NISA共通の特典) |
満期まで引き出しにくい学資保険に比べ、こどもNISAは汎用性が高いのが特徴です。
進学のタイミングだけでなく、急な支出や将来の独立資金にも活用できる柔軟性があります。
実際どうする?子どもの教育資金を準備する3つの選択肢
こどもNISAがまだ制度化されていない現在、子どもの教育資金をどうやって準備するかは多くの家庭にとって悩ましいテーマです。
ここでは、現実的に選べる3つの方法を紹介します。
選択肢① 学資保険でコツコツ積立
最も伝統的な方法が「学資保険」です。
毎月決まった額を積み立て、一定の時期に受け取る仕組みで、貯金感覚で運用できる安心感があります。
- メリット:元本確保、満期受取金が確定している
- デメリット:途中解約に弱い、利回りは低め
日本は年率2%のインフレを目指しており、学資保険の利回りは年率1%前後なので、現在のようなインフレ(物価高)が続けば学資保険の価値はハッキリ言ってなくなります。
選択肢② 親のNISA口座で運用する
こどもNISAが始まる前に活用できるのが、親のつみたてNISAや成長投資枠です。
教育費を目的に、子ども名義ではなく「親の非課税枠」で長期運用する家庭が増えています。
- メリット:非課税で運用できる、投資先を自由に選べる
- デメリット:親の資産として扱われるため、贈与の際に注意が必要
選択肢③ こどもNISAで運用する
2026年から開始予定のこどもNISAを活用して、長期で積立投資をすれば、子どもが大学に入る年齢になれば、かなりの金額になっていることが期待できます。
- メリット:子ども用資金として「名義をはっきり分けられる」
非課税で運用できる - デメリット:親の口座を分けることで、管理の手間がかかる
私は子供手当+αを全て、旧ジュニアNISAで運用して、かなりの運用益が出ましたので、この資金をさらに2026年からのこどもNISAで運用する予定です。
こどもNISAの制度化に向けた注意点と留意事項

こどもNISA(こども支援NISA)はまだ制度化前の段階ですが、実現すれば家庭の資産形成にとって大きな変化となる可能性があります。
ただし、利用にあたっては注意すべき点もいくつかあります。
名義の問題:親と子ども、どちらの口座で管理するか?
こどもNISAが制度化されれば、子ども名義のNISA口座が可能になる見通しです。その際、以下のような点に注意が必要です:
- 贈与扱いになるかどうか(親の資金を使う場合)
- 子どもが18歳以上になったときの名義移管
- 金融教育と意思決定のサポート体制
投資リスクの認識
こどもNISAは「非課税=元本保証」ではありません。
制度ができたとしても、損失は自己責任となります。
制度の詳細と変更に注意
こどもNISAもまた、導入時点では未完成な制度である可能性があります。
だからこそ、柔軟に対応できるよう複数の準備手段を並行して持つことが賢明です。
こどもNISAが始まったら?我が家の選び方とシミュレーション
こどもNISAが正式に制度化されたら、実際にどのように活用すればよいのでしょうか?
ここでは、家庭の状況や子どもの年齢に応じた選び方のポイントを整理してみます。
運用期間で選ぶと失敗しにくい
- 短期(3年以内):学資保険や預金が無難
- 中期(5〜10年):こどもNISAで積立投資が有効
- 長期(10年以上):こどもNISA+個別投資や親NISAの併用もあり
子どもの年齢別!活用のタイミングと戦略
| 子どもの年齢 | おすすめ戦略 |
|---|---|
| 0〜5歳 | 長期運用スタート。つみたて中心で育てる |
| 6〜12歳 | 教育費ピークに備え中期運用 |
| 13〜17歳 | 元本確保も検討。リスク低めの投資信託へ |
まとめ:柔軟な設計と“学びのきっかけ”として活用を
こどもNISAは、単なる資金準備ツールにとどまらず、子どもと一緒に「お金を学ぶ」チャンスにもなります。
これらを通じて、子どもの金融リテラシーが自然と育っていくことも、大きな価値といえるでしょう。
まとめ
こどもNISAはまだ制度化前ですが、将来の教育資金を準備する上で大きな可能性を秘めた制度です。
従来の学資保険と比べ、自由度や利回りの面で優れる一方、元本保証がない点など注意も必要です。
だからこそ、現時点では「親のNISAを活用する」「特定口座で積立を始める」など、できることから柔軟に備えておくことが大切です。
制度が始まったときにスムーズに移行できるよう、今から選択肢を比較し、家庭に合った戦略を考えておきましょう。

-
-
機関投資家の動きを個人投資に活かす方法
株式投資は「自分が良いと思う銘柄」を選んでも必ずしも勝てません。重要なのは“みんなが買う銘柄”を見極めること。まるで「1位を当てる美人投票」のように、市場全体が注目する銘柄に乗ることが、値上がりの波に ...
-
-
黒字転換株の選び方と3つの注意点
「赤字続きだった企業が、黒字になった瞬間に株価が急騰した」――そんな事例を見て、「自分もあのタイミングで買っておけば…」と思ったことはありませんか? この記事では、注目される前に仕込める“黒字転換株” ...
-
-
コスパ最強!米国株アプリおすすめはコレ
米国株投資を始めたいけれど、「どの証券会社のアプリがいいの?」と悩んでいませんか?最近は取引手数料が無料のところも増え、選ぶ基準は“コスパ”と“アプリの使いやすさ”が重要になっています。 本記事では、 ...
-
-
【体験談】スマホで簡単!moomoo証券の口座開設方法を画像付きで紹介
「moomoo証券の口座開設って難しそう…」そんな風に感じていませんか?私も最初は不安でしたが、実際にスマホだけで簡単に手続きができ、驚くほどスムーズに口座開設が完了しました。 この記事では、実際の操 ...
-
-
財務データで読み解くクァンタムスケープ|いつ黒字転換できるのか?
革新的な全固体電池で注目されるクァンタムスケープ。私自身もこの企業に投資しており、将来性には大きな期待を寄せています。 しかし、現時点では売上ゼロ・赤字継続という不安要素も多く、慎重な見極めが必要です ...
-
-
セレブラスの上場時期はいつ?IPO延期の経緯と2026年Q2目標の最新動向
セレブラス(Cerebras Systems)は、AI向けの超大型チップ(ウェハースケール)で注目される半導体企業です。「いつ上場するの?」「2025年と言われていたけど結局どうなった?」と気になって ...