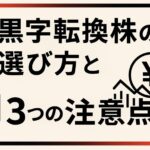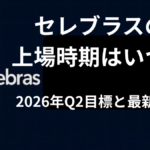「ビュージックスって、実際のところ将来性あるの?」——そんな疑問に、投資歴5年の僕がビュージックスの将来性についてまとめました。
ビュージックスは、いわゆる「スマートグラス(メガネ型デバイス)」の中でも、工場や倉庫などの現場で使うことに特化したメーカーです。

ビュージックスの CEO 兼創設者であるポール・トラバース氏は「Amazon Inc.は倉庫内の機器メンテナンスにVuzixのメガネを使用している」と述べています。
こうした事例を見ると、「ただの未来ガジェット」ではなく、実際の現場で役に立つ道具として広がりつつあることが分かります。
一方で、「夢は大きいけど、売上や利益はまだこれから」という段階でもあります。
この記事では、
- そもそもビュージックスとはどんな会社なのか
- 将来性を考えるときに、どこに注目すれば良いのか
- 投資するうえで気をつけたいポイントは何か
を、できるだけかみ砕きながらお話しします。
※本記事の内容は情報提供を目的としたものであり、特定企業への投資を推奨するものではありません。
投資に関する意思決定は、ご自身の判断と責任にてお願いいたします。
ビュージックス(VUZI)の会社概要

ビュージックスは現場用のスマートグラスを設計、製造する企業です。
ビュージックスのスマートグラスが使われる場面として、例えば次のような現場があります。
- 倉庫での荷物のピッキング(見つけて運ぶ)作業
- 工場での組み立てや検査
- 設備の点検やメンテナンスを遠隔からサポートする場面
これらの仕事では、今まで「紙の指示書」や「ハンディ端末」を片手に持ちながら作業することが普通でした。
しかし、スマートグラスを使うと、手をふさがずに、目の前のレンズに必要な情報を映し出しながら作業できるようになります。

新人でもある程度の作業は一人でできるようになりますし、難しい作業でもマニュアル片手にしなくてもよくなります。
ビュージックスの主な製品イメージは次の2種類です。
- 現場作業向けのがっちりしたモデル(耐久性・装着感・視認性を重視)
- 見た目が普通のメガネに近い、軽量フレーム型モデル(長時間つけても疲れにくいことを重視)
イメージしやすいように、一般向けスマートグラスとの違いを簡単に表にすると、こんな感じです。
| 観点 | ビュージックスのような業務用スマートグラス | 一般消費者向けスマートグラス |
|---|---|---|
| 主な用途 | 遠隔支援、作業手順の表示、作業記録 | 通知の表示、写真・動画撮影、エンタメ |
| 重視される点 | 壊れにくさ・見やすさ・サポート体制 | デザイン・価格・遊び心 |
| 買い手 | 企業(部署や本社) | 個人ユーザー |
| 成功のポイント | 作業時間の短縮、ミスの減少などの「数値効果」 | 使っていて楽しいか、便利だと感じるか |
まずはこの違いを押さえておくと、ニュースを読むときに「これはビュージックスにとって追い風かどうか」を判断しやすくなります。
ビュージックスの将来性のカギはどこ?(成長ドライバー)
僕がビュージックスの将来性を考えるときに、特に大事だと思っているポイントは次の3つです。
1)「現場でラクになる」が数字で証明できるか
スマートグラスは、導入した瞬間に全社へ一気に広がる製品ではありません。多くはトライアル→効果検証→拠点追加という順番です。だからこそ、導入事例が「どの工程で、どの指標が改善したか」まで具体的になってくるほど、テーマが“思いつき”から“投資”に変わっていきます。
2)軽さ・見やすさ・電池など「使い勝手」が現場基準を満たすか
現場で1日つけるなら、少しの不快感が致命傷になります。重さ、視認性、バッテリー、ヘルメットや度付きとの相性——こうした地味な条件を満たして初めて「使い続けられる道具」になります。ここは派手さより改善の積み上げが重要です。
3)提携(OEM)とAI連携で“使い道”が広がるか
ビュージックスは、単体デバイスの販売だけでなく、他社ブランドの製品に技術を組み込むOEMや、クラウド/業務システムとセットでの展開が伸びしろになります。さらに生成AIと組み合わさると、作業手順の提示、翻訳、映像からの異常検知など「現場でAIを使うための画面」としての価値も上がります。
ビュージックスの最新動向(2025年末〜2026年1月)
まず業績面。
2025年Q3(9月30日までの四半期)は売上が約116万ドル(前年同期比▲16%)、純損失は約735万ドルで、依然として赤字です。
一方で、営業費用は前年同期比で減少し、現金・現金同等物は約2,260万ドルでした。
経営陣は、Q4での製品売上・エンジニアリング売上の伸びを見込み、複数のOEM案件の進捗や“大手オンライン小売企業向けの高額バックログ(6桁台)”の消化が追い風になる、という趣旨を述べています。
次回決算(市場予想ベース)は、2026年3月12日前後が目安として案内されており、赤字幅と売上の回復が注目点になりそうです。
次にニュース面です。
- 2025年12月19日:Collins Aerospace(RTX傘下)との協業継続を発表。波導(ウェーブガイド)系の表示エンジン開発が進み、2026年に向けて低率量産(LRIP)から本格展開を狙う文脈が示されています。
- 2026年1月5日:CES 2026で、AI対応スマートグラスや波導ソリューションをエコシステムパートナーと展示。企業向け導入を進めやすくする新たなGo-to-Market戦略にも触れています。
- 2026年1月7日:Himax Technologiesと、度付き対応も想定した“処方対応の軽量AR光学リファレンスデザイン”を共同発表。量産しやすい光学プラットフォームを打ち出しました。
黒転ハンター視点でいうと、ニュースの良し悪しより「数字に変わるか」を見たいところです。
具体的には、①売上が四半期ごとに安定して増えるか、②粗利(もしくは粗損)が改善して“固定費を吸収できる形”に近づくか、③営業キャッシュフローのマイナスが縮むか。
この3点が揃い始めると、黒字転換の現実味が一段上がります。
投資で気をつけたいリスク
注意点は大きく3つです。
1つ目は、市場の立ち上がりが想像以上に遅い可能性。トライアルが増えても、売上が数字に乗るまで時間がかかります。
2つ目は、競合・価格・導入ハードル。企業は本体だけでなく、保守・教育・システム連携まで含めた総コストで比べます。
3つ目は、業績の波と資金繰り。B2Bは大型案件で四半期の数字が凸凹しやすく、赤字が続けば追加の資金調達(増資など)も意識する必要があります。
僕のスタンス(追いかけ方)
ここからは、完全に僕個人のスタンスです。
ビュージックスのような銘柄とは、どのくらいの距離感で付き合うのが現実的だと感じているかを書いておきます。
ビュージックスは、「現場DX(デジタルで現場のやり方を変えること)×スマートグラス」という、非常に分かりやすいテーマに乗った企業です。
一方で、その立ち上がりはどうしても段階的で、数年単位で見ていく必要があるタイプだと感じています。
だからこそ、僕は「夢だけで突っ走る」のではなく、ある程度ルールを決めて付き合う銘柄だと捉えています。
まとめ
ビュージックスの将来性は、「現場のKPIを改善できる道具として定着するか」にかかっています。
2025年Q3時点では赤字が続く一方、現金は約2,260万ドルを確保しつつ、2025年末〜2026年初には防衛領域の協業継続や展示、光学リファレンスデザインの発表など、パートナー連携のニュースが出ています。
黒字転換を狙う視点では、「大型案件が“単発”から“継続・横展開”に変わった」と見える瞬間を待つ。
ここが見えてくると、数字の読み方も変わってくるはずです。
ビュージックスを狙うなら大口の売買通知機能があるmoomoo証券がオススメ、公式サイトはコチラ
-
-
黒転投資とは?メリット・デメリットと成功のコツ
「黒転投資って聞いたことあるけど、なんだか難しそう…」そんな方にこそ知ってほしい、実はシンプルで魅力的な戦略があります。 黒転投資とは、赤字企業が黒字に転換する“転換点”を狙う投資手法。タイミングを掴 ...
-
-
機関投資家の動きを個人投資に活かす方法
株式投資は「自分が良いと思う銘柄」を選んでも必ずしも勝てません。重要なのは“みんなが買う銘柄”を見極めること。まるで「1位を当てる美人投票」のように、市場全体が注目する銘柄に乗ることが、値上がりの波に ...
-
-
黒字転換株の選び方と3つの注意点
「赤字続きだった企業が、黒字になった瞬間に株価が急騰した」――そんな事例を見て、「自分もあのタイミングで買っておけば…」と思ったことはありませんか? この記事では、注目される前に仕込める“黒字転換株” ...
-
-
コスパ最強!米国株アプリおすすめはコレ
米国株投資を始めたいけれど、「どの証券会社のアプリがいいの?」と悩んでいませんか?最近は取引手数料が無料のところも増え、選ぶ基準は“コスパ”と“アプリの使いやすさ”が重要になっています。 本記事では、 ...
-
-
【体験談】スマホで簡単!moomoo証券の口座開設方法を画像付きで紹介
「moomoo証券の口座開設って難しそう…」そんな風に感じていませんか?私も最初は不安でしたが、実際にスマホだけで簡単に手続きができ、驚くほどスムーズに口座開設が完了しました。 この記事では、実際の操 ...
-
-
財務データで読み解くクァンタムスケープ|いつ黒字転換できるのか?
革新的な全固体電池で注目されるクァンタムスケープ。私自身もこの企業に投資しており、将来性には大きな期待を寄せています。 しかし、現時点では売上ゼロ・赤字継続という不安要素も多く、慎重な見極めが必要です ...
-
-
セレブラスの上場時期はいつ?IPO延期の経緯と2026年Q2目標の最新動向
セレブラス(Cerebras Systems)は、AI向けの超大型チップ(ウェハースケール)で注目される半導体企業です。「いつ上場するの?」「2025年と言われていたけど結局どうなった?」と気になって ...
-
-
証券会社のAI機能を比べてみた
「証券会社のAIって、どこも同じに見える…」そんなふうに思っていませんか?実は、AI機能の内容や使いやすさは、証券会社によって大きく違います。moomoo証券のように、銘柄分析や決算の要約までサポート ...