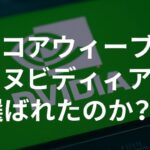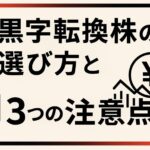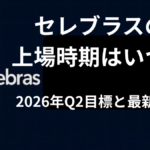「コアウィーブの黒字化はいつになるのだろう?」と気になっている方へ。
AIインフラを支える注目企業コアウィーブは、上場後も赤字が続いているものの、その成長スピードと戦略から見て、黒字化はもはや“時間の問題”と言える段階に来ています。
本記事では、最新の決算情報やマイクロソフト・エヌビディアとの関係、大型買収の影響まで、投資判断に役立つ情報をやさしく解説します。
コアウィーブって何者?上場後の現状まとめ
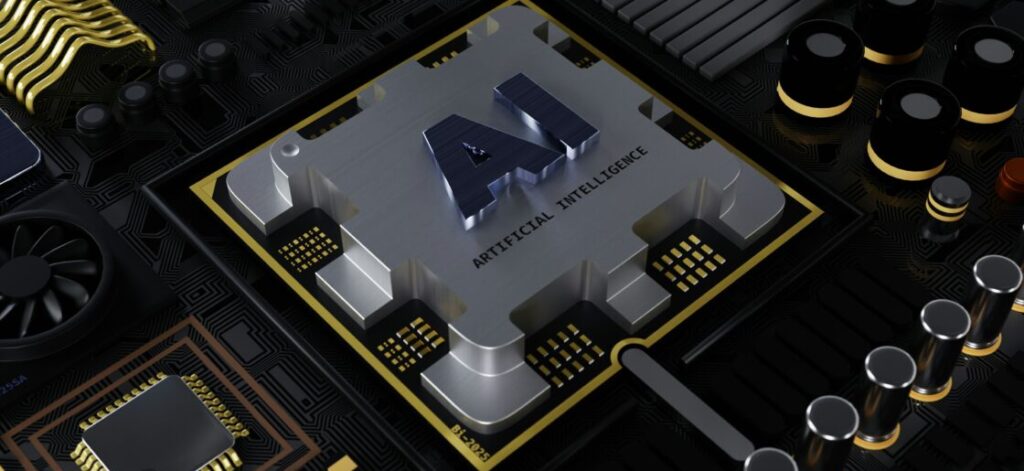
NASDAQ上場〜株価はどこまで上昇したか
コアウィーブ(CoreWeave)は、2024年にNASDAQへ上場したAI向けクラウドインフラ企業です。
生成AIや機械学習に特化した高性能GPUクラウドを提供することで、注目を集めています。
上場時点での時価総額は約160億ドルとされており、エヌビディアとの提携を背景に、AIバブルの波に乗って急騰。
特に注目を浴びたのは、エヌビディアのGB200 Grace Blackwell搭載GPUを最速で導入した企業のひとつである点です。
株価は一時的に調整を挟みつつも、AI関連のニュースと連動して再浮上する局面が見られるなど、ボラティリティの高い動きを見せています。
強力なエヌビディア・マイクロソフトとのパートナーシップ
コアウィーブの成長を支えているのが、エヌビディアとマイクロソフトとの深いパートナー関係です。
- エヌビディアとの関係性
エヌビディアは初期からコアウィーブに出資しており、GPU供給でも優遇されています。
特にAI開発向けの最先端GPUを安定的に供給できることは、競合との差別化につながっています。 - マイクロソフトとの契約
2024年にはマイクロソフト・アジュールとの間で、数十億ドル規模の契約を結んだと報じられました。
これにより、大規模AIトレーニング需要を取り込むことに成功しています。
このように、大手との信頼関係をベースに急成長しているのが、現在のコアウィーブの立ち位置です。
-
-
なぜコアウィーブはエヌビディアに選ばれたのか?
エヌビディアが自社GPUのパートナーに選んだクラウド企業「コアウィーブ」。近年その名を耳にする機会が増えたけれど、なぜこの企業が注目されているのでしょうか? 本記事では、エヌビディアとの技術的・資本的 ...
データセンターの拡充とGB200導入実績
2025年に入り、コアウィーブは米国内のデータセンターを急速に拡大しています。
- 拠点数:全米で10以上の拠点に展開
- 電力規模:累計で5GW以上の供給を目指しているとされる
特に注目されたのは、エヌビディアの最新GPU「GB200 Grace Blackwell」をいち早く導入した点です。
これにより、生成AIの学習速度・コスト効率が大幅に向上し、大規模AI企業からの需要もさらに増加することが見込まれます。
GPU供給の面で有利な立場を保ちながら、物理インフラでも着実に基盤を築きつつある――これが今のコアウィーブの実力です。
赤字でも勢いは止まらない?黒字化の目安とは

最新決算(2025年Q1)で見える収益構造
CoreWeaveは2025年現在、急成長を続ける一方で、依然として赤字状態が続いています。
しかし、その赤字には「成長のための先行投資」という明確な理由があります。
例えば、2025年Q1の決算では以下のような特徴が見られました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売上高 | 前年同期比で+400%以上の成長 |
| 粗利益率 | 改善傾向にあるが依然として低水準 |
| 純損失 | データセンター関連コストやGPU調達費が重荷。前年同期比-143% |
| キャッシュフロー | 新株発行や資金調達に依存して黒字維持中 |
つまり、「売上は伸びているが、コストも同時に急拡大しており、まだ利益が追いついていない」という状況です。
GPU調達や減価償却の影響を整理
赤字の主な要因となっているのが、GPU調達費用とデータセンター建設にかかる減価償却費です。
- GPUはエヌビディアからの優遇供給があるものの、単価は高額
- 建設コストも短期的には収益を圧迫する
- エネルギーコストや冷却設備への設備投資も負担に
とはいえ、これらは「一時的なコスト」であり、ある程度の稼働率と顧客数の確保ができれば黒字化可能な構造です。
今後の収益改善には何が鍵?
コアウィーブが黒字化に至るための鍵は、大きく以下の3点です。
- データセンター稼働率の最適化
- 大口顧客の獲得と長期契約化
- 運営効率の改善(自動化・AI最適化)
これらの戦略がうまくいけば、2026年中の黒字化も視野に入ると予測されます。
注目の大型買収「コア・サイエンティフィック統合」で黒字化へ前進
買収内容・スケール感(約90億ドル)
2025年、コアウィーブはAIインフラの拡張を目的として、仮想通貨マイニング大手「コア・サイエンティフィック」を約90億ドルで買収する方針を発表しました。
この買収の背景には、次のような思惑があります。
- コア・サイエンティフィックが保有する大規模な電力供給能力
- 米国南部に集中する安価な電力ネットワーク
- 既存のマイニング設備をAI向けデータセンターに転用可能
これにより、コアウィーブは自社のAIクラウド基盤を一気に拡大できるというわけです。
コスト圧縮と債務圧力の軽減効果
この買収により、コアウィーブにはいくつかのコスト的メリットが生まれます。
- 設備の共通利用により初期投資の圧縮が可能
- 電力コストの抑制(1kWhあたり3〜5セント)
- 既存資産を活用することで減価償却の負担も軽減
また、コア・サイエンティフィック側は破産手続きから再建中の企業であり、再編の一環としてコアウィーブの事業と統合されることで財務的な相乗効果が期待されています。
売上・利益にどう影響するか?
この統合が完了すれば、コアウィーブの売上基盤は一段と広がると見られています。
- GPUクラウド需要の受け皿となる物理インフラが拡充
- エンタープライズ顧客への高性能クラウドサービス提供が加速
- 規模の経済によって1案件あたりの利益率が改善
仮にこの買収が予定どおり完了し、設備の稼働が進めば、黒字化は「2026年にも現実的」と見るアナリストもいます。
投資家目線でここに注意!リスクと株価シナリオ

顧客集中リスク(マイクロソフト依存の実態)
コアウィーブは急成長中とはいえ、収益源が一部の大口顧客に偏っている点はリスクです。特に、
- マイクロソフトとの契約に大きく依存
- Azure向けのAIインフラ供給が全体の収益を左右
- 顧客の戦略変更や契約終了が即業績に響く
という構造になっています。
増資・株式希薄化の影響
コアウィーブは巨額の設備投資を続けており、資金調達のための増資(新株発行)が繰り返される可能性もあります。
- 買収資金や設備費用でキャッシュフローは常に逼迫気味
- 2024年以降、数回にわたってプレIPO・ポストIPOの増資実施
- 株式数が増えるたびに、既存株主の持ち分は薄まる
長期的な成長を信じて保有する場合、一時的な株価の下落や調整も覚悟する必要があります。
競合との比較とバリュエーション
AIインフラ市場は、コアウィーブだけが主役ではありません。以下のような競合も勢いを増しています。
| 企業名 | 特徴 |
|---|---|
| ラムダ | AI向けGPUクラウド提供、独自OSとソフト開発も強み。エヌビディアから投資 |
| セレブラス | AI専用チップと独自ハードウェアの開発で差別化 |
| ヴォレント | マルチクラウド対応のAI推論基盤で成長中 |
こうした企業と比較して、時価総額や利益率が正当化できるか?という点も、投資判断のポイントとなります。
まとめ|黒字化は「時間の問題」と言えるか?
コアウィーブは、上場後も赤字が続いているとはいえ、成長スピード・提携関係・インフラ拡張のどれを見ても「時間の問題」と言えるほどに黒字化に近づいています。
特に、コア・サイエンティフィックの買収やマイクロソフトとの継続契約など、今後の収益基盤はますます安定化する見込みです。
もちろん、投資にはリスクもつきものですが、「成長を先取りしたい」という投資家にとって、コアウィーブは注目すべき存在であることは間違いありません。

-
-
機関投資家の動きを個人投資に活かす方法
株式投資は「自分が良いと思う銘柄」を選んでも必ずしも勝てません。重要なのは“みんなが買う銘柄”を見極めること。まるで「1位を当てる美人投票」のように、市場全体が注目する銘柄に乗ることが、値上がりの波に ...
-
-
黒字転換株の選び方と3つの注意点
「赤字続きだった企業が、黒字になった瞬間に株価が急騰した」――そんな事例を見て、「自分もあのタイミングで買っておけば…」と思ったことはありませんか? この記事では、注目される前に仕込める“黒字転換株” ...
-
-
コスパ最強!米国株アプリおすすめはコレ
米国株投資を始めたいけれど、「どの証券会社のアプリがいいの?」と悩んでいませんか?最近は取引手数料が無料のところも増え、選ぶ基準は“コスパ”と“アプリの使いやすさ”が重要になっています。 本記事では、 ...
-
-
【体験談】スマホで簡単!moomoo証券の口座開設方法を画像付きで紹介
「moomoo証券の口座開設って難しそう…」そんな風に感じていませんか?私も最初は不安でしたが、実際にスマホだけで簡単に手続きができ、驚くほどスムーズに口座開設が完了しました。 この記事では、実際の操 ...
-
-
財務データで読み解くクァンタムスケープ|いつ黒字転換できるのか?
革新的な全固体電池で注目されるクァンタムスケープ。私自身もこの企業に投資しており、将来性には大きな期待を寄せています。 しかし、現時点では売上ゼロ・赤字継続という不安要素も多く、慎重な見極めが必要です ...
-
-
セレブラスの上場時期はいつ?IPO延期の経緯と2026年Q2目標の最新動向
セレブラス(Cerebras Systems)は、AI向けの超大型チップ(ウェハースケール)で注目される半導体企業です。「いつ上場するの?」「2025年と言われていたけど結局どうなった?」と気になって ...