
企業が次々と過去最高益を更新し、内部留保(企業の貯金)も600兆円を超える中、なぜ私たちの暮らしは一向に楽にならないのでしょうか?
税負担は軽くなったはずの企業に対し、私たちは消費税や社会保険料というかたちでじわじわと家計を圧迫されています。
この記事では、投資家の視点から、日本の税政策がどのように企業と国民に“異なる重力”で働いているのかを読み解きます。
法人税と消費税の使い分け、海外との比較、そして政策が企業にもたらす長期的リスクとは──。
「成長」と「分配」のバランスを問い直すヒントを、静かに掘り下げていきます。
企業は過去最高益、なのに暮らしは苦しいのはなぜ?

2024年、企業の利益はまたしても過去最高を更新しました。
財務省が発表した法人企業統計によれば、企業の利益から税金や配当などを差し引いた「内部留保(利益剰余金)」は、2023年度末時点で600兆9,857億円に到達。
初めて600兆円を超え、なんと12年連続で過去最高を更新しています。
この記録的な好業績の背景には、円安による輸出企業の利益拡大や、海外需要の回復などがあります。
とくに大手企業の中には、海外売上比率が高いことから為替差益で大きく利益を押し上げた例も見られます。
ところが、私たち国民の暮らし向きはどうでしょうか。
総務省や厚労省の統計を見ると、実質賃金は下落傾向が続き、物価上昇に給与が追いついていない状況です。
食品や日用品、電気・ガス代といった生活必需品の値上がりが家計を直撃しており、多くの人が「景気がいいなんて実感がない」と口にします。
この“実感なき景気回復”の最大の原因は、企業が得た利益の多くが内部留保として溜め込まれ、設備投資や賃上げといった形で社会に還元されていないことです。
Business Journalの記事でも、設備投資や人件費の伸びは鈍く、内部留保の活用が課題だと指摘されています。
つまり、企業がいくら利益を出しても、それが雇用や消費に循環しなければ、経済の下支えにはならないのです。
加えて、政治の側が企業の利益を出しやすい環境を整えていることも、格差を広げる一因となっています。
法人税は過去に比べて引き下げられたままであり、一方で消費税は10%に据え置かれたまま。
その結果、家計への負担が強まる中、企業は税負担を軽くしながら利益を蓄積している構図が続いています。
このような“企業は好調だが国民は苦しい”というギャップは、政策設計と再配分のあり方を見直す必要があることを強く示唆しています。
法人税と消費税はどう使い分けられているのか?
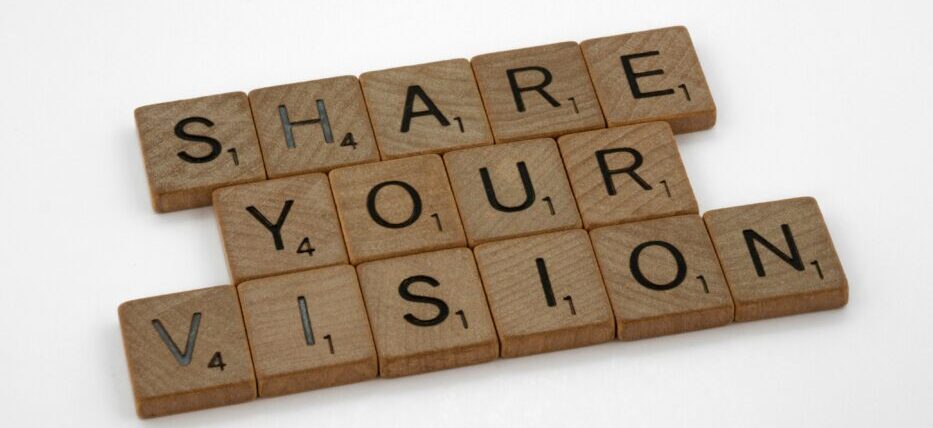
日本の税制を見渡すと、法人税は引き下げられてきた一方で、消費税は引き上げられ据え置かれているという構図が浮かび上がります。
この違いは、単なる税目の選択ではなく、国の財政運営と再分配の姿勢を象徴するものです。
まず、法人税は過去30年間で大きく引き下げられました。
かつて40%を超えていた税率は段階的に下げられ、現在では実効税率で約29%前後。
その理由として政府は、「国際競争に打ち勝つため」「企業の投資や雇用を促進するため」などを掲げてきました。
たしかに、グローバル企業の競争は激化しており、税率が高すぎれば企業の海外移転や投資回避につながるというリスクはあります。
しかし一方で、税率を下げ続けることで、国の税収構造は大きく変化しました。
それを補う形で導入・強化されたのが消費税です。
1989年に3%で導入されて以来、5%・8%・10%と段階的に引き上げられ、いまや年間約22兆円の税収の柱になっています。
問題は、この消費税の「逆進性」です。
所得が少ない人ほど、生活に必要な支出の割合が高くなり、その分、収入に対する税負担が重くなるのです。
つまり、消費税は見かけ上は「公平」でも、実質的には低所得者ほど負担が大きいという仕組みです。
このようにして、「企業は税率が下がり、国民は消費で負担する」という流れが定着してきました。
財務省や政府は「社会保障の安定的な財源」として消費税の維持を正当化していますが、実際には企業への減税を埋め合わせる形で使われてきたという面も否めません。
税とは単なる徴収の手段ではなく、どこから取り、どこに配分するかという“哲学”を持つものです。
そして、政府はその税金の使い方を考える機関でもあります。
法人税と消費税の使い分けが、結果として格差を助長していないか、今こそ問い直されるべきではないでしょうか。
海外では不景気にどう対応している?──アメリカ・欧州との比較

日本では、不景気でも消費税が据え置かれ、法人税の増税も行われないまま、国民の負担が増えるという構造が続いています。
では、海外──特にアメリカやヨーロッパ諸国ではどうなのでしょうか?
結論から言えば、アメリカや欧州は不景気時に「減税」や「一時的な税優遇」で積極的な景気刺激策を講じる傾向があります。
これは政府が経済を「動かす手段」として税制を柔軟に使っているからです。
● アメリカの場合:減税と財政出動で企業・家計を支援
アメリカでは、景気後退期に法人税の減税や税控除の拡大がよく用いられます。
たとえば、2020年のコロナショックでは「CARES法(コロナ経済対策法)」によって、企業は過去の損失をさかのぼって申告できる「欠損金繰戻し(NOL carryback)」制度が復活し、過去の利益と相殺することで税金が還付されるという仕組みが導入されました。
これにより企業の資金繰りが大きく支援されました。
また、個人にも現金給付や失業保険の拡充が迅速に行われ、“お金を回す”ことに重きが置かれた対応でした。
さらに特徴的なのは、アメリカには日本のような全国一律の消費税(VAT)は存在しないことです。
州ごとに異なる「Sales Tax」があり、不景気時には一時的に免除されたり、「Tax Holiday(消費税の休日)」のような生活必需品の減税キャンペーンが行われることもあります。
● ヨーロッパの場合:付加価値税(VAT)の一時的減税で消費刺激
ヨーロッパでは、消費税にあたる付加価値税(VAT)を一時的に引き下げる政策が取られることがあります。
たとえば、
- ドイツ(2020年):VATを標準税率19%から16%に引き下げ(期間限定で半年間)
- イギリス(2020年):飲食・観光業を対象に、VATを20%から5%に減税
これらは一時的な措置ではありますが、「消費を刺激し、事業者の売上回復を支える」という即効性ある政策として機能しました。
● なぜ日本は税制を柔軟に使えないのか?
対して日本は、「財政再建」を最優先に掲げており、不景気でも税率を下げる余地がないという立場を取りがちです。
特に消費税は、社会保障の財源と位置づけられているため、増税後は“下げにくい”構造になっています。
その結果、不景気であっても企業支援には慎重、消費税も据え置き、国民生活に冷たい印象を与える政策運営が続いているのです。
海外と比較すると、日本の税制は“硬直的”とも言える状況です。
「景気に応じて税制を柔軟に運用する」ことができるか否かが、経済の回復力や国民の生活実感に大きく影響することが見て取れます。
好景気になっても法人税はなぜ上がらないのか?

企業の利益が伸び、株価も堅調──そんな好景気の局面でも法人税が引き上げられることはほとんどありません。
むしろ、法人税率は長期的に見ると世界的に下落傾向にあり、日本も例外ではありません。
その背景には、経済のグローバル化と政治の現実があります。
● グローバルな税率競争の存在
法人税が引き上げにくい最大の理由は、国際的な税率競争です。
グローバル企業は利益を低税率国に移しやすく、税率が高すぎる国からは資本や雇用が流出するリスクがあります。
そのため各国は、「他国より法人税率を高くしすぎない」ことに非常に慎重です。
たとえば、アメリカではトランプ政権が2017年に法人税を35%から21%へ大幅に引き下げました。
バイデン政権はこれを28%へ再引き上げようと試みたものの、企業界や議会の反発を受けて頓挫しています。
このように、法人税の引き上げは政治的にも経済的にもハードルが非常に高いのです。
● 好景気なら税収は増える。だから税率を上げる必要がない?
もう一つの理由は、「好景気で企業利益が増えれば、税率を変えなくても税収が自動的に増える」という事実です。
税率が一定でも、企業の利益が増えれば、それに応じた法人税が徴収されるので、政府としては無理に税率を上げなくても“景気に乗って”収入が増えるというわけです。
そのため、好景気時にはあえて法人税率に手を付けず、そのまま様子を見るという戦略が採られがちです。
● 政治的に“増税”は不人気
さらに見逃せないのが、政治的な忖度です。
法人税の引き上げは経済界や経団連などから強い反発を受けやすく、与党にとっては選挙での支持を失うリスクを伴います。
とくに日本では、経済団体の影響力が強く、大企業の意向が政策に反映されやすい構造があります。
その結果、たとえ景気が回復しても、法人税の引き上げが議論に上がることすら少なく、「企業はそのまま減税メリットを享受し続ける」という流れが固定化されてしまうのです。
● 世界では“最低法人税率”の動きも
ただし、世界全体としては、過度な税率競争を抑えるために「最低法人税率を設けよう」という動きも出ています。
たとえば、OECD主導で進められている「グローバルミニマム課税(最低15%)」は、タックスヘイブンへの逃避を防ぎ、公正な法人課税の土台づくりを目指すものです。
とはいえ、これも各国の利害が絡むデリケートな問題であり、実効性を持たせるにはまだ時間がかかりそうです。
結局のところ、好景気でも法人税が上がらないのは、単に「上げたくない」のではなく、「上げられない」構造と論理があるのです。
投資家としては、こうした政策の背景を理解することが、企業業績の持続性や株価の動きを見通す上で重要な視点となります。
投資家として見た政策の“歪み”とリスク

法人税が下げられ、消費税が上げられる。
企業は利益を出し続け、内部留保は積み上がる──こうした構造は、一見すると投資家にとってはポジティブな環境に見えるかもしれません。税負担が軽くなれば企業の純利益は増え、EPS(1株当たり利益)も上昇し、株価の支えとなる要素がそろいます。
しかし、投資家として本当に注目すべきなのは、短期の業績ではなく「その政策が持続可能かどうか」という視点です。
そして、今の日本の経済構造にはいくつかの“歪み”が存在し、それが中長期的なリスクとなり得ることを見過ごすべきではありません。
● 消費の冷え込みが内需企業の足を引っ張る
まず、日本の家計は長らく賃金が上がらず、可処分所得も伸び悩んでいます。
さらに消費税などの負担が重なれば、当然ながら消費マインドは冷え込みます。
これは内需型の企業──たとえば小売・飲食・住宅・サービス業など──にとって明らかなマイナス材料です。
仮に法人税が下がっても、需要が伸びなければ売上も利益も伸びません。つまり、「企業全体にとって減税は良い」とは一概には言えないのです。
● 経済の二極化が進み、投資先が偏るリスク
次に、政策が特定の企業や業界に有利に働くことで、“勝ち組”と“負け組”の格差が広がるというリスクもあります。
実際、大企業は海外収益や為替差益によって業績を伸ばしている一方で、中小企業や国内中心の企業は取り残されているという構図が浮かび上がっています。
投資家の視点では「勝ち組企業だけ選べばいい」と思うかもしれませんが、市場全体の健全性が損なわれると、長期的にはリスクプレミアムが上がり、ボラティリティが高くなるという副作用もあります。
● 社会全体が疲弊すれば、企業も成長できない
もう一つ重要なのは、「企業は社会の一部である」という基本的な事実です。
企業がいくら利益を出しても、社会全体が貧しくなれば購買力は落ち込み、企業の成長余地は限られるようになります。
また、若者が希望を持てず、消費を控え、人口が減り続ける国で、持続的な経済成長は困難です。
短期的には企業業績が良く見えても、市場そのものが縮小していくならば、投資リターンの最大化は望めません。
● 歪みに気づける投資家が未来をつかむ
こうした政策の“歪み”を読み解く力は、今後ますます重要になります。
財務諸表や決算書だけを見ていても、本質的な企業価値は見えてきません。
むしろ、政府がどの方向に舵を切ろうとしているのか、それによって社会構造はどう変わるのか──このような視点を持つことで、真に持続可能なビジネスモデルを持つ企業や、逆風下でも成長できる企業を見極める力が養われていきます。
投資家にとって最大の武器は、「数字を超えて社会を読む力」です。
短期的な税制メリットの裏に潜む“ひずみ”を直視することが、未来への最良のリスクヘッジとなるでしょう。
まとめ──企業成長と国民の幸福は両立できるのか?
本記事では、日本の税政策が企業寄りに設計されている実態と、その背景にある国内外の事情を見てきました。
法人税は下がり続け、消費税は上がったまま。
企業は内部留保を膨らませる一方で、国民の実質賃金は伸びず、生活のゆとりは感じられない――そんな“歪んだ構図”が今の日本には存在しています。
しかしここで考えたいのは、「企業の成長と国民の幸福は対立するものなのか?」という問いです。
答えはNOです。
本来、企業が利益を上げ、その利益が従業員の賃金や国内への投資、地域経済への貢献につながれば、それは家計を潤し、消費を刺激し、さらなる成長の循環を生み出すはずです。
つまり、企業の成長と国民の幸福は両輪として回るべきなのです。
では、何がその連動を妨げているのでしょうか?
ひとつは、企業が「守り」に入って内部留保をため込みすぎていること。
もうひとつは、政府が再分配機能を十分に果たしていないこと。
法人税を下げ、消費税で補うという構図は、社会全体の購買力をじわじわと削ぐ政策にもなりかねません。
だからこそ、これから必要なのは、国民の可処分所得を回復させる政策転換です。
賃上げを促す制度設計、中小企業支援、所得税や社会保険料の見直し、さらには生活必需品への軽減税率の再検討など、「使えるお金を増やす」政策こそが、日本経済を内側から温める鍵になるでしょう。
投資家としても、こうした社会構造の変化に敏感であることは重要です。
短期の決算数字だけでなく、長期的な需要の源泉である“暮らしの豊かさ”が、どのように政策で支えられているかを読む力が、これからの投資判断を左右していくはずです。
企業が強くなり、国民も豊かになる。
その両立は、決して夢物語ではありません。
必要なのは、誰のための成長かを問い直す視点と、そこに適切な資金の流れを生み出す政策です。
私の考え
今回の参議院議員選挙でも、この法人税や内部留保について、不公平だと言及していたのは、私の知る限りでは日本共産党だけでした。
しかし、日本共産党に政権を任せられるはずもありません。
企業献金の打ち切りを恐れずに、法人税や内部留保にメスを入れる政治家がいればなぁと思います。
ちなみに具体的には
- 法人税を上げる:これは「国際競争力が…」という反論に合うと考えられます。
- 内部留保に対する課税をする:私はコレがベストだと思います。
内部留保に対する課税を行えば、企業は嫌でも賃上げや設備投資、自社株買いを実行するでしょう。
ただし、上場企業はおそらく自社株買いばかりするでしょうから、賃上げや設備投資にお金を振り分けさせる方策が必須です。
もし、内部留保に対する税率が5%ならこれだけで消費税を廃止してもお釣りがでます。
※2024年度の消費税による税収約25兆円、内部留保課税5%なら約30兆円
そもそも、景気を良くするためにはお金の流れを良くする必要があります。
そのためには、企業の内部留保を一般人に流れる仕組みを作らなければならないのです。
-
-
内部留保600兆円の時代に、消費税10%据え置き──政策の狙いを投資家はどう読むか
企業が次々と過去最高益を更新し、内部留保(企業の貯金)も600兆円を超える中、なぜ私たちの暮らしは一向に楽にならないのでしょうか?税負担は軽くなったはずの企業に対し、私たちは消費税や社会保険料というか ...
-
-
株の情報収集に強いアプリ5選
株の情報収集、何から始めればいいのか迷っていませんか?SNSやネットの噂は多いけど、信頼できる情報源を自分で見つけるのは意外と難しいもの。そんなときに役立つのが「株の情報収集に特化したアプリ」です。 ...
-
-
証券会社のAI機能を比べてみた
「証券会社のAIって、どこも同じに見える…」そんなふうに思っていませんか?実は、AI機能の内容や使いやすさは、証券会社によって大きく違います。moomoo証券のように、銘柄分析や決算の要約までサポート ...
-
-
勝てない理由はコレ!機関投資家のルールとは
「自分が買うと株価が下がる…」そんな経験、ありませんか?もしかすると、その裏には機関投資家のルールに基づいた売買が関係しているかもしれません。 本記事では、個人投資家が知らない機関投資家の動きや売買ル ...
-
-
黒字転換で株価3倍も?個人投資家はココを狙え!
「黒字転換した企業の株価が3倍に跳ねた」――そんなニュースを目にして、乗り遅れたと悔しい思いをしたことはありませんか? 本記事では、そもそも黒字転換とは何かから始まり、株価が上がるメカニズムや急騰事例 ...





